おむつを着用しているお子様の尿検査で、多くの保護者の方が最も苦労されるのが「採尿」です。健康診断で採尿バッグを渡されても、「うまく貼れない」「嫌がって剥がしてしまう」「皮膚がかぶれてしまった」といった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、おむつ着用児の採尿には根本的な課題があります。医学的に理想とされる「中間尿採取」や「完全な清潔性の確保」は、現実的に困難だということです。
この記事では、そうした現実を踏まえた上で、採尿バッグ、代替法、新しい選択肢「ゆらりす」を客観的に比較し、お子様とご家族に最も適した方法を見つけるための情報をお伝えします。完璧な解決策は存在しませんが、「より良い選択」を一緒に考えていきましょう。
採尿の基本原則:清潔性と中間尿採取の重要性
まず、医学的に理想とされる尿検査の要件を理解しておきましょう。これらの要件は、正確な検査結果を得るための重要な基準です。
清潔性
尿検査において重要なのは「清潔性」です。雑菌や汚染物質が混入すると、本来陰性(値が0または低い)であるタンパク質や白血球の項目で、汚染により陽性(値が基準より高い)と判定されてしまう「偽陽性」となる可能性があります。
以下の方法で清拭(せいしき)をすることで、便や皮膚の雑菌が尿に混入し、偽陽性のリスクを下げられます。
清拭の手順
- 物の準備
- 清潔なタオルまたはガーゼ
- 必要に応じて微温湯
- 清拭:陰部全体を優しく、しっかりと清拭
- 女の子の場合:前から後ろへ(尿道口から肛門方向へ)
- 男の子の場合:包皮を軽く下げて清拭
- 乾燥
- 水分をしっかり拭き取る
- 完全に乾燥させる(湿った状態では採尿バッグが貼り付かない)
中間尿の採取
医学的に最も推奨されるのは「中間尿」の採取です。
- 初尿(出始めの尿):尿道口付近の雑菌を洗い流すため、最初の尿は捨てる
- 中間尿(途中の尿):最も清潔な部分を採取
- 終わりの尿:そのまま排出
中間尿採取により、尿道口付近の雑菌混入を最小限に抑え、より正確な検査結果を得ることができます。
おむつ着用児の採尿における現実的課題
しかし、以下の根本的な問題から、おむつを使用している重症心身障害児においては、医学的に必要とされているこれらの条件を完全に満たす採尿方法が存在しないのが現実です。
- 中間尿採取の困難
- 排尿のタイミングを予測できない
- 出始めの尿を捨てることができない
- 途中で採尿を開始することが技術的に不可能
- 一定時間の尿貯留による汚染リスク
- 尿が一定時間貯留されることで雑菌が繁殖する可能性
- 直接陰部に触れた尿が回収される
- 装着過程での汚染リスク
つまり、医学的な理想と現実にはギャップがあり、どの採尿方法を選択しても、おむつ着用児からは医学的に理想とされる条件を完全に満たした尿を採取することはできないという認識を持つことが必要となります。
おむつ着用児の採尿方法比較|採尿バッグ・代替法・ゆらりす
医学的理想を完全に満たせない現実の中で、それでも最善の選択肢を検討する必要があります。以下、主要な3つの方法を客観的に比較します。
採尿バッグ(採尿パック)|医療機関標準の採尿方法
医療機関で最も広く使用されている方法で、学校の健康診断でも配布されます。
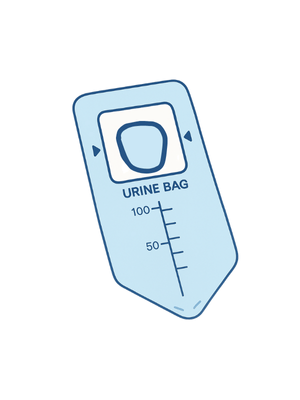
特徴
- 陰部に粘着テープで貼り付けるビニール製の袋
- 医療機関での標準的な小児採尿法
- 比較的多量の尿採取が可能
採尿バッグ特有の課題
- 皮膚への負担:粘着テープによる皮膚損傷、アレルギー反応のリスク
- 装着の技術的困難:特に女児での正確な貼り付けには熟練が必要
- 時間的負担:長時間つけられないので、学校の定期検診では採尿の準備で忙しい朝の時間が圧迫されてしまう
コットン・ガーゼ法|採尿バッグの代替手段
採尿バッグが使用できない場合の代替案として使用されます。

実施手順
- おむつ内にラップまたはビニールを敷く
- その上に清潔なコットンやガーゼを配置
- 排尿後、濡れたコットンを手で絞って尿を採取
コットン・ガーゼ法特有の課題
- 混入リスクの増大:繊維や処理剤の混入可能性
- 採取量の限界:十分な量の採取が困難な場合がある
- 手技の煩雑さ:準備と採取過程が複雑
- 衛生的な尿処理の限界:尿を集めたコットン・ガーゼを手で絞る必要があり、非衛生的
採尿サポートパッドゆらりす®︎(新たな選択肢)
ゆらりす®︎は、おむつ利用者にとって尿検査の本質的要件を満たす手段が存在しない現実の中で、従来の採尿バッグとコットン・ガーゼ法の問題解消を目指して開発された製品です。
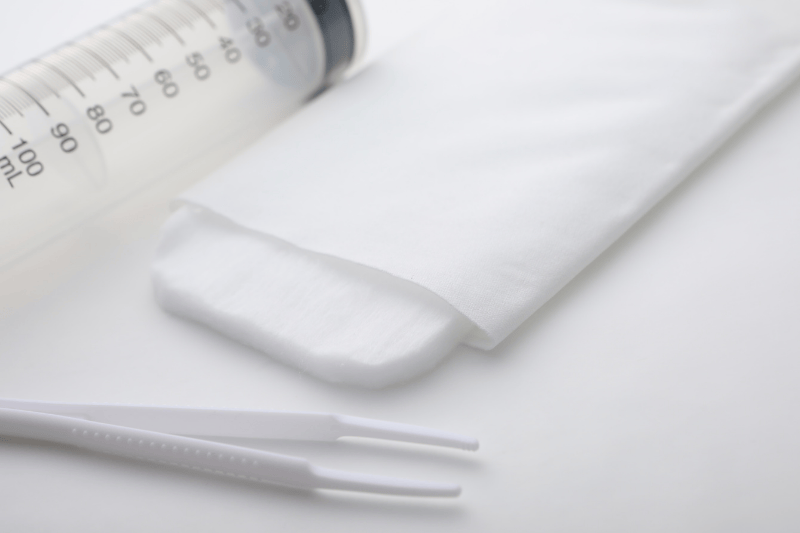
特徴
- 保護者の負担軽減
- おむつ内への簡単な設置で済み、煩雑な物の準備や貼り付け技術が不要
- 十分量の尿が取れない失敗を減らし、採尿のやり直しによる負担を軽減
- 衛生的に尿を回収できる
- お子様の肌保護
- 粘着テープ不使用により皮膚の損傷を回避
- スポーツウェア素材使用でかぶれリスク軽減
- アレルギー反応のリスク軽減
使用方法
- 通常の清拭・乾燥を実施
- おむつ内にゆらりすを適切に配置
- 通常通りの生活で排尿を待つ
- 採尿コア(脱脂綿部分)を絞って尿を容器に移す
ゆらりす特有の課題
採尿コアに一定時間尿を保持することによる検査結果への影響については、今後検証を行う必要があります。
製品詳細
詳しい製品情報や使用方法は、プロダクトページをご覧ください。
採尿方法の選択指針|お子様の状況に応じた最適な選択
現在の採尿方法には、それぞれに課題があり、より適切な方法を確立するための研究が今後も必要です。しかし、そうした検証結果を待つ間も、必要に応じてお子様の健康管理を継続していく必要があります。
皆様ご自身で評価できるポイント
保護者の皆様が採尿方法を選択される際は、以下の点を考慮されることをお勧めします。
- お子様の個別状況: 皮膚の状態(かぶれやすさ、アレルギーの有無)や、過去の採尿経験での成功・失敗パターン
- 保護者ご自身の状況: 採尿技術への習熟度や失敗によるストレス度合い
かかりつけ医との相談で確認すべきポイント
以下の項目については専門的な判断が必要になるため、必要に応じて医師に相談されることをお勧めします。
- お子様特有のリスク評価: 基礎疾患に適した採尿方法の選択
- 検査結果の適切な解釈: 採尿方法の制約を考慮した結果の解釈と追加検査の必要性
- 継続的な健康管理の方針: 定期検査での方法統一の必要性やお子様の成長や状況変化に応じた見直し
ポイント:完璧な解決策は今のところ存在しないため、「より良い選択」「より継続可能な方法」を医師と一緒に見つけていくという姿勢が大切です。
重症心身障害者における尿検査の意義
重症心身障害児や一部の医療的ケア児においては、完璧ではない採尿方法であっても、尿検査を実施することの意義について考える必要があります。
前回の記事でお伝えした通り、重症心身障害児は健常児と比較して腎障害や代謝異常のリスクが高いという報告があります。この現実を踏まえると、以下のような考え方も重要です。
- 早期発見の重要性: 異常の早期発見を試みる上では、完璧ではない検査でも、全く検査をしないよりも多くの情報を得られる可能性があります。
- 変化を捉える重要性: 検査結果の傾向を把握することで、その傾向の変化を捉えることで体調の変化に気づくことができる可能性があります。
検証が不完全な現状でも、重症心身障害児の高い疾患リスクを考慮すると、「検査をしない」という選択よりも、「利用可能な方法で検査を継続する」ことの方が、お子様にとって有益な可能性があります。
この判断は、お子様の具体的な状況とかかりつけ医の見解を総合して行うことが大切です。採尿方法の制約はありますが、それでも得られる情報を活用してお子様の健康を見守っていくことが、現実的で建設的なアプローチといえるでしょう。
まとめ:継続可能な採尿方法の選択に向けて
おむつを着用するお子様の採尿は決して簡単ではありませんが、この記事でお伝えしたポイントを参考に、お子様とご家族に最も適した方法を見つけていただければと思います。
- 完璧を求めすぎない
- どの方法にも制約があることを理解する
- 「より良い選択」を目指すという現実的な姿勢を持つ
- お子様とご自身の状況を重視する
- 皮膚の状態や過去の経験を考慮する
- ご家族の技術的習熟度や心理的負担も大切な要素
重症心身障害児は健康リスクが高いからこそ、完璧ではない検査であっても、継続的な健康状態の把握に活用できる可能性があります。「何もしない」よりも「できる範囲で続ける」ことで、お子様の健康を見守っていけると考えています。
かかりつけ医と一緒に、お子様の成長とともに最適な方法を見つけていただければと思います。私たちも可能な範囲でご相談への対応をさせていただきます。
次回は、採取した尿を用いた検査結果の読み解き方と、異常値が出た時の適切な対応について詳しく解説します。
参考文献
医学文献・ガイドライン
- 日本小児泌尿器科学会:「小児の尿路感染」診療指針
https://jspu.jp/ippan_014.html - 日本腎臓学会:「一般臨床医のための検尿の考え方・進め方」
https://jsn.or.jp/guideline/kennyou/09.php - 厚生労働省:「医療的ケア児者とその家族の生活実態調査報告書」(2020年)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00004.html - MSDマニュアル:「細菌性尿路感染症」(2023年6月22日)
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/03-泌尿器疾患/尿路感染症-uti/細菌性尿路感染症
採尿技術・検査方法
- シスメックスプライマリケア:「試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)」解説
https://primary-care.sysmex.co.jp/speed-search/detail.php?pk=564 - 大久保駅前・林クリニック:「尿検査で分かること」(2022年1月30日)
https://okubo-hayashi-clinic.com/archives/216 - 看護roo!:「尿検査」解説記事 (2015年7月22日)
https://www.kango-roo.com/learning/1478/
重症新障害児特有のリスク
- 東京都立小児総合医療センター:「尿路感染症」診療指針
https://www.tmhp.jp/shouni/section/internal/nephrology-04.html - 慶應義塾大学病院:「尿路感染症」KOMPAS医療情報
https://kompas.hosp.keio.ac.jp/disease/000252/ - MSDマニュアル:「カテーテル関連尿路感染症」(2023年6月22日)
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/03-泌尿器疾患/尿路感染症-uti/カテーテル関連尿路感染症
この記事について
※実際の検査や治療については、必ずかかりつけ医にご相談ください
監修: 河村峻太郎(医師、ゆらりす代表)
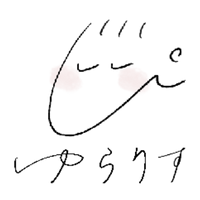
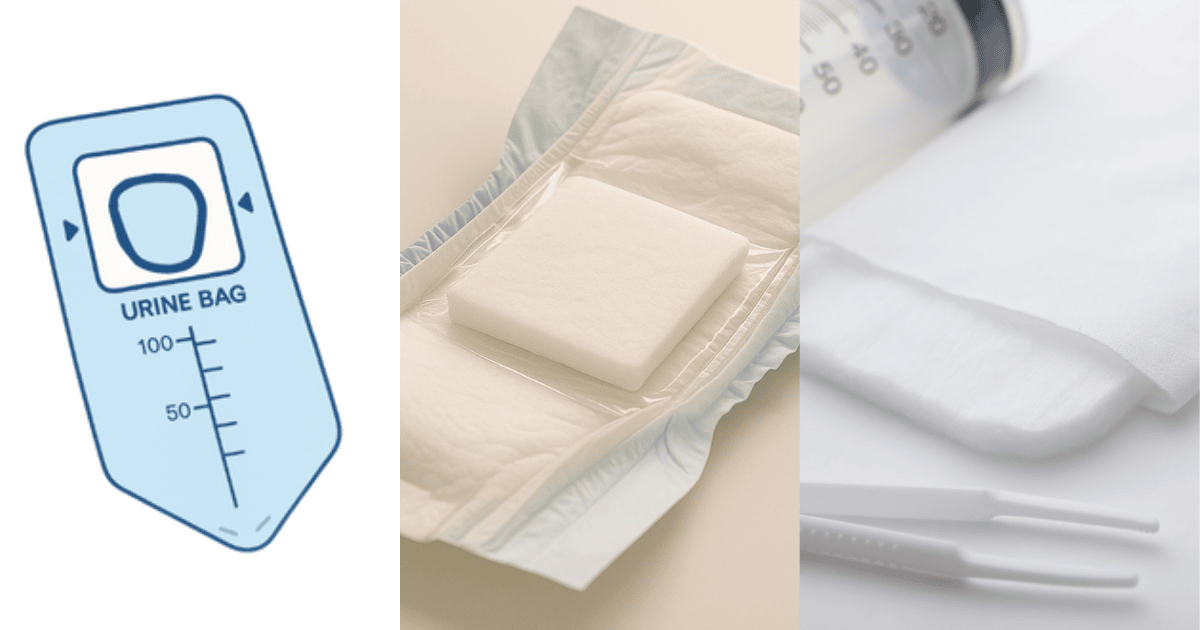
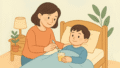

コメント